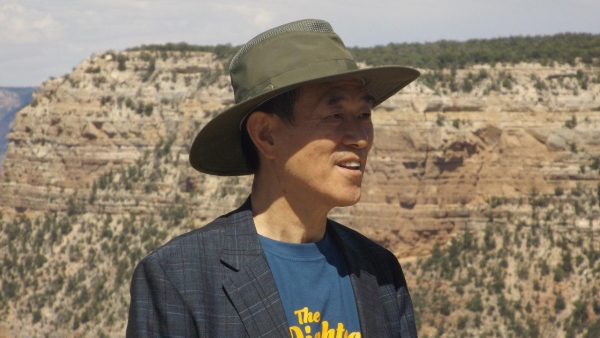
1. ユダの裏切りとイエス様の最後の愛の勧め
ヨハネの福音書13章20〜30節には、「ユダがそのパン切れを受け取ると、すぐに出て行った。すでに夜であった」(ヨハネ13:30)という一節とともに、イエス様を裏切ったユダの姿が生々しく描かれています。この場面は弟子たちが共に取った最後の晩餐の情景の中で起こり、そこにはイエス様が示される徹底した愛の勧めと、それを最後まで拒否するユダの姿が対照的に浮かび上がっています。張ダビデ牧師は、この箇所を通して「主の愛は人間の自発的な決断や悔い改めを強制しない」という点を深く強調します。すなわち「神様は私たちをむりやり翻意させたり操作したりはなさらない」ことは、愛という本質自体が強制ではなく、自由な選択に基づくものであるという大前提を示すのです。そしてこの"自由"という賜物の前で人はどのように反応するのかを、ユダの事例をもって際立たせているのです。
イエス様がパン切れを直接ユダに手渡された行為は、単なる食卓でよくある所作ではありませんでした。パレスチナ地域の文化的背景を考えると、誰かに直接パンをちぎって手渡すことは、特別な愛と敬意の表れでもあったのです。それほどまでにイエス様は最後の最後までユダを受け入れ、誰よりも近しい席に置き、心からの思いを伝えようとなさったのです。その過程で、弟子たちの足を洗われる出来事も同時に起こります。そこに至るまでイエス様が示された愛の歩みは、徹底した"仕える姿勢"と"勧め"のメッセージに満ちています。弟子たちはその姿に感動し涙し、もしかすると主のことばを噛みしめながら自分たちのメシア観を新たに整理していたかもしれません。しかしその中にあっても、ユダだけはイエス様の愛を完全には受け入れず、すでに心の奥深くに裏切りの種を抱えていました。
張ダビデ牧師は、ここで「主が最も近くに置かれた弟子が主を売った」という点を通して、私たち自身の内面を振り返る必要があると強調します。ユダは何よりも"金銭"を預かる者でした。ユダヤ人共同体、特にメシア共同体の中でお金を管理するということは、大きな信頼が前提となる行為です。一般的に金銭は誘惑を引き起こしやすく、争いや紛争の火種となる可能性が高いため、責任感と霊的成熟を兼ね備えた人に委ねられることが多いのです。ところがイエス様は、その金銭箱をユダに任されました。これはイエス様がユダを深く信頼し、他の誰よりも大きな責任と信頼を置いておられたことを意味します。張ダビデ牧師は「主は最後までユダを信じておられた」と解釈し、その信頼は決して強制や"釣り餌"ではなかったことを強調します。神様には「絶対的な愛の予定」しか存在しないからです。それにもかかわらずユダは、自身の内面に潜む世俗的欲望と歪んだ視点のゆえに、主の勧めを受け入れませんでした。
香油の壺を砕いた女性の出来事は、そうしたユダの心を決定的に表面化させる場面です。ある女性が非常に高価な香油の入った壺を砕いてイエス様に捧げたとき、ユダはその純粋な愛の表現を「貧しい人々のためにその費用を使ったほうがよかったのではないか」という、世俗的で実利的な観点から批判しました。もちろんその言葉自体だけ見れば、貧しい人々を助けることが悪いとか間違っているというわけではありません。しかし問題なのは、愛を愛として受け取れず、敬虔の核心がイエス様への全身全霊の献身であることを理解せず、計算的にアプローチした点にあります。イエス様の歩みは世の常識から見ると愚かに映ったり、非効率的に見えたりするかもしれません。ですがその道は本質的に愛の道であり、十字架の道であり、自己犠牲による救いの道なのです。ユダはその道を理解しませんでした。いや、正確には理解しようともしなかったのかもしれません。張ダビデ牧師によれば、まさにそこに「蛇よりも醜い罪性」がユダの内に露わになるのだと言います。
主の最後の晩餐の場面は、ヨハネの福音書13章で頂点に達します。イエス様は「まことに、まことにあなたがたに言いますが、あなたがたのうちのひとりがわたしを裏切ります」と直接的に告げられます。それを聞いた弟子たちは互いに顔を見合わせ、「いったい誰のことを言っておられるのだろうか」と戸惑いに陥りました。ところが主は、その裏切り者が"ユダ"であることを即座に名指しして暴露されるわけではありませんでした。代わりに「わたしがパン切れを浸して与える者がその人だ」と言い、直接それをユダに手渡します。この行為は裏切り者を明らかにすると同時に、彼に最後まで愛を示す象徴的な行動でもありました。パン切れを浸して渡すというのは親密さを示す行為でもありますが、それがユダに与えられたときには警告のメッセージも含まれています。「わたしはあなたの心にあることを知っている。しかし今でもいい、立ち返りなさい。このパンを通してもう一度戻って来なさい」という招きです。けれどもユダはその招きを無視し、パン切れを受け取ると、すぐに外へ出て行ってしまいました。
ヨハネは「ユダがそのパン切れを受け取ると、すぐに出て行った。すでに夜であった」と記します。この「夜」という表現は、単に時間帯を伝えているだけではなく、ユダの霊的状態や世の暗黒が具体化するイメージをあわせ持っています。夜とは闇であり、隠れであり、罪と堕落を象徴する時であり、同時にイエス様がただひとりでその道を歩まれる決定的な瞬間でもあるのです。愛の勧めがこれ以上通用しない時、裏切りが現実化する時、霊的な闇が具体的な形を取る時、それがまさにこの夜というわけです。張ダビデ牧師は、この「夜」の意味が単なる時間的出来事を超え、「神様を離れるすべての魂が陥る闇」を指し示していると指摘します。つまり、私たちも主の愛を拒み、立ち返らなければ、この暗闇へと入ってしまう可能性があることを戒めるのです。
さらにこの箇面で注目すべきは、ユダが外へ出て行くのを見ても、弟子たちは別段おかしいと思わなかったという事実です。何人かは「ユダは財布を管理しているから祭りに必要なものを買いに行ったのだろう」とか、「貧しい人々に何かを分け与えに行ったのだろう」と推測します。彼らは事態の深刻さにまったく気づいていませんでした。ユダの心の中心に広がっていた裏切りの種を、誰も見抜けなかったのです。こうしたことは、現代の教会共同体の中でも十分に起こり得ます。最も近くにいる兄弟姉妹でさえ、互いの霊的状態を明確に把握できないこともあるのです。張ダビデ牧師は、私たちが常に目を覚まして祈り合い、恵みの内で真実な交わりを持つことの重要性を説きます。たとえ愛の共同体でも、霊的な無知や無関心が重なると、その中に潜む危機を察知できずに大きく膨れ上がってしまう可能性があるからです。
では、ユダの裏切りはどこから始まったのでしょうか。先に触れた香油の壺を割った事件を見れば、結局ユダは世の論理にどっぷり浸かっていたと考えられます。イエス様の道を正しく見つめず、また見ようともしませんでした。主のことばや勧めを聞いても、自分の欲望や偏見をもって判断しようとし、その結果、イエス様に対する愛の情熱や献身をむしろ"浪費"と見なしていた可能性が高いのです。さらに決定的には、イエス様が描かれる神の国が、彼が期待していた政治的解放や世俗的栄光とは違うものであると知って失望したのかもしれません。イエス様が示される自己を低くするリーダーシップ、罪人や貧しい人々への寛容、何よりも「十字架」へと向かう犠牲的な姿勢は、ユダが望んだ革命的リーダー像とはかけ離れて見えたのでしょう。
ユダは最後の機会に至るまで、主の愛を拒み続けます。彼がパン切れを受け取って外へ出て行ったということは、すなわち「彼の選択が確定した」ということでもあります。愛は強制しません。張ダビデ牧師はこれを「神様の痛み」として解釈します。全能の神様が、人間に自由意志を与えられたゆえに、人が自ら罪を選び裏切りの道を歩むのをそのまま見ておられるのです。このように神様の愛は無限ですが、それを最後まで拒み続ける人は、最終的には永遠の闇へと入ってしまいます。そしてヨハネの福音書のこの場面を通して私たちは、その闇の入り口でイエス様が伸ばされる手を容赦なく振り払うユダの頑なさを見るのです。
私たちはユダを「恐ろしい裏切り者のひとり」と断じて終わりにするのではなく、現代を生きる私たちの心の奥にも同じような暗闇の一面が潜んでいるかもしれない、と自省すべきです。長年教会に通い、御言葉を聞き、奉仕や献金に励んでいても、心の片隅に世俗的な基準で主のみわざを判断しようとする態度が潜んでいるかもしれません。自分の限界を感じるとき、本来なら主のもとに行き悔い改めるべきところを、「それは違うんじゃないか?もっと実用的な方法があるのでは?」と批判的かつ冷笑的な姿勢で愛の行いを値引きしてしまうことがあります。また、役職や奉仕、財政管理を任されている人ほど、ますます謙遜に自分自身を顧みる必要があります。ユダが"金銭箱"という重要な務めを任されていたにもかかわらず堕落したように、人間は誰しもつまずく可能性があるからです。
ユダの裏切りは単なる歴史的出来事ではなく、今日の私たちの歩みに対する警鐘です。イエス様の愛のことばが語られ、悔い改めと立ち返りを促す最後の機会がいくらでも与えられているのに、それを拒否して無視することもできるのだ、という事実を示しています。神様は最後まで愛してくださいますが、最後まで立ち返らず闇へ向かおうとする者を無理には止められません。張ダビデ牧師は、この点を通して「私たちは常に警戒心を持って主に立ち返らなければならない」と力説します。御言葉を聞いて黙想する場は、常にユダがパン切れを受け取った場と同じです。それは私たちを生かすものにもなり得ますが、同時に立ち返らなければ裁きを招くこともあり得ます。このようにヨハネの福音書13章に描かれる最後の晩餐の場面は、主の愛が最高潮に達すると同時に、人間の裏切りが劇的に明るみに出る場面でもあります。そしてその二つの極の狭間には、"立ち返りの機会"が存在するのです。
弟子たちの中でもペテロもまた主を否認しましたが、最終的には悔い改めて戻って来ました。しかしユダはそうしませんでした。ペテロの否認は恐れと弱さから出たものでしたが、彼の心の奥底にはそれでも主を愛する思いが残っていました。そのため涙をもって悔い改めることができたのです。一方のユダは、彼自身の野心と欲望が深く根差しており、裏切りをあらかじめ計画し、実際に行動に移しました。その裏切りは悔い改めや立ち返りではなく、絶望と自殺に終わってしまいます。こうして人間の内面に潜む罪の歴史の深さと恐ろしさが、私たちにまざまざと示されます。そして同時に、それは私たち誰にでも起こり得る悲劇的可能性を示唆しているのです。
また、晩餐を取り囲む弟子たちの様子からは、ユダが出て行く瞬間まで彼らが状況を正確に把握していなかったことも分かります。もし弟子たちがもう少しユダの状態をよく見守り、彼の言動から現れる異常な兆しを察知していたなら、もっと早く彼を引き留め、悔い改めるよう勧められたかもしれません。けれども弟子たちはそれを知らなかったのです。これはある意味、私たちの現実と重なります。私たちのすぐそばにいる誰かが深い絶望に陥り、罪の誘惑に敗れ、ついには教会を離れて世俗の暗闇に沈み込んでいく過程を、周囲がまったく気づかないまま見過ごしてしまうことがあまりに多いのです。ですから、日々御言葉と祈りによって互いを顧み、霊的に覚醒していなければ、人の心が深い闇に陥るのを防ぐことは難しい。それが人間の共同体の弱さでもあるのです。
主の愛は最後まで両腕を広げて私たちを招いておられます。ヨハネの福音書13章20節でイエス様は「わたしが遣わす者を受け入れる者は、わたしを受け入れるのであり、わたしを受け入れる者はわたしを遣わされた方をも受け入れるのです」と明確に言われました。これはイエス様を信じ受け入れることが、そのまま父なる神を受け入れることを意味するということです。そしてユダはこのことばを聞いたにもかかわらず立ち返らなかったということは、単に師を裏切っただけでなく、神を受け入れること自体を拒否した行為だったとも言えます。張ダビデ牧師は「誰も主の御心を無理矢理ひっくり返すことはできない」と解釈します。愛は相手の自由な決断なしには成り立たないので、ユダが最後まで引き返さないことをイエス様も強要して止めることはなさらなかった、というのです。
さらにユダの例から私たちが常に心に刻むべきことは、「悔い改めの機会はいつでも与えられるが、それが永遠に与えられ続けるわけではない」という点です。ユダは明らかに最後の晩餐でパン切れを受け取り、その前にも何度となくイエス様のことばや愛のしるしを直接目にしていました。それにもかかわらず心を入れ替えず、最後のチャンスさえも逃してしまったのです。これこそ、罪の闇が人の内面にどれほど深く根を下ろし得るのかを示す恐ろしい姿です。そして最終的に闇が臨んだとき、彼の魂は回復不能な絶望の中へと引き込まれてしまいました。
こうしてヨハネの福音書13章が示すユダの裏切りの出来事は、単に昔の弟子共同体の中で起こった衝撃的な悲劇として終わりません。むしろ私たち一人ひとりがイエス様の愛を日々どのように受け止めているか、あるいは拒んでいるかを顧みるよう促しているのです。私たちは主の愛を、聖餐のパンのように毎瞬受け取っています。御言葉を通して、共同体の礼拝を通して、宣べ伝えられる福音を通して、互いに分かち合う愛の交わりを通して、私たちは絶えず主に立ち返る機会を得ているのです。けれどもユダのように霊的無知や頑なさに捕らわれ、そのすべての機会を逃してしまうこともあり得るということを、常に自覚していなければなりません。張ダビデ牧師はこれを一種の「神様の無力さ」と表現します。全能の神であっても、愛という名のもとでは人間の自由意志の前に無力に見える場合がある、というわけです。しかしこの無力さこそが神の愛の最も劇的な表現なのです。私たちを強制的に従わせるのではなく、自発的な決断による立ち返りを待たれるからです。
「ユダがそのパン切れを受け取ると、すぐに出て行った。すでに夜であった」(ヨハネ13:30)ということばは、私たちに決断を迫るメッセージとして迫ってきます。人生の中で日々数多くの選択をする中で、私たちは主の勧めに従って立ち返るのか、それとも最後まで背を向けて闇を選ぶのか。これこそがユダの裏切りの物語が投げかける究極の問いです。張ダビデ牧師が強調するように、私たちの中にユダのような頑なさが潜んではいないか、日々御言葉と祈りによって点検する必要があります。そしてどのようなときも、主の愛が最後まで私たちに向けて開かれていることを、決して忘れてはなりません。裏切りが闇の道へ向かう選択ならば、愛は光の道で私たちをつかむ招きです。この二つの道のどちらへ進むのかという決断は、結局私たち自身に委ねられているのです。
2. 霊的無知と悔い改めの機会
ユダが裏切りの道を歩み始めたとき、弟子たちはまったくその裏切りの気配を察していませんでした。イエス様が「あなたがたのうちのひとりがわたしを裏切る」と直接警告されたにもかかわらず、彼らは互いに「いったい誰のことを言っておられるのだろう?」とひそひそ話をするだけでした。さらにはイエス様がパン切れを浸してユダに渡される際にも、その行為が何を意味するかをはっきり理解しませんでした。そしてユダが外に出て行くと、「何かを買いに行ったのだろう」「貧しい人々を助けに行ったのだろう」と考える程度だったのです。このように霊的無知は共同体を危機に陥れます。これは古代の弟子共同体だけの話ではありません。現代の教会共同体も同様に、周囲で起こる大小さまざまな霊的危機を、正しく把握せずにやり過ごしてしまうことが多いのです。
張ダビデ牧師はここで「霊的な緊張感と目を覚ましていること」の重要性を強調します。イエス様は何度も弟子たちに語り、象徴的な行いをもって裏切りの影を示されていました。足を洗われながら「互いに仕え合いなさい」と言われ、香油の壺を割った女性の献身を通して「愛」の本当の意味を明かされました。そして最後の晩餐の直前には「あなたがたのうちのひとりがわたしを裏切る」とはっきり宣言されました。けれども弟子たちは、その愛の意味やイエス様の言葉を十分に咀嚼しきれないまま、ユダの裏切りがまさに進行中であることにも気づきませんでした。これはすなわち、愛が冷め、霊的に鈍感になっているときに生じる典型的な現象でもあります。いつもイエス様と共にいたにもかかわらず、その御心を十分に悟れず、共同体内部に潜む罪の種を見抜けなかったのです。
弟子たちがユダの心を事前に知り、その行動を阻止できたかどうかは定かではありません。しかし少なくとも、イエス様が間接的に示された裏切りの兆候をもう少し深刻に受け止めていれば、ユダにもっと注意を払い、なんとか引き止めようと試みることはできたかもしれません。それこそが愛の共同体が果たすべき役割でしょう。現代の教会でも、もし誰かが信仰の道から外れ始めたり、世俗的欲望に深くとらわれている兆しが見えたとき、安易に裁いたり排除したりするのではなく、どうにか最後まで抱きとめ、立ち返るよう助ける努力が必要です。これはその人の魂のためだけでなく、共同体全体にとっても大切な道です。というのも、一人の人が罪の暗闇に陥るとき、その影響はしばしば本人だけにとどまらないからです。
ただし、ユダが裏切りの道を進みながらも、弟子たちが誰ひとり疑わなかったという事実は、逆説的に言えばユダがそれほど"共同体の中で信頼されていた存在"であったことをも示しています。財布を預かるほどに信頼されていた人物が、内に罪を抱え墜ちていく可能性があることは、「信仰的地位」や「役職」が罪からの免疫を保証しないという重要な教訓を投げかけます。むしろ役職や責任が大きいほど誘惑も多く、いったん倒れたときの影響も大きい。張ダビデ牧師はこれを「教会の指導者や奉仕者ほど目を覚ましている必要がある」というメッセージに広げていきます。名誉や肩書の陰に隠れて、自分の内に潜む罪性や世俗的欲望を隠しやすくなるからです。最終的にユダが神様の愛と共同体の信頼を徹底的に裏切り、外へ出て行ってしまう姿は、決して他人事ではありません。
本質的に「御言葉の場」とは、パンを割いて与えてくださる場所であり、私たちが心を改める機会が与えられる場所でもあります。張ダビデ牧師はこれを「ユダがパン切れを受け取ったその瞬間、そこには彼にとって最後の機会があった」と解説します。イエス様の愛が、そのパン切れの中に余すことなく込められていました。つまり、もしユダがその愛を受け入れる決心をしていたなら、事態は変わっていたかもしれないのです。そこにこそ、悔い改めと救いの神秘が宿っています。人はどんな極限の絶望や罪の鎖に縛られていても、ある一瞬に心を開き主の愛を受け入れるなら、奇跡のように変えられる可能性があるのです。ところがユダは、その奇跡の瞬間を無視しました。パンを受け取るなり外へ出て行き、"夜"の中へ消えてしまったのです。これはすなわち、彼が頑なさの道を選び取ったことを意味します。
ここで私たちは「人が悔い改めず、自分の罪性を最後まで手放さないとどうなるのか?」という恐ろしい結末を目の当たりにします。その結果は信仰の破綻です。ユダは主に対する裏切りだけでなく、その後の自責の念に陥り、ついには自死という結末に至りました。もし真に悔い改めて立ち返っていれば、ペテロのように再び赦しを受け、回復の道を歩むことができたかもしれません。しかし彼はその道を選ばなかったのです。したがって、ペテロとユダはどちらも「主を否認し、裏切った」形になりましたが、一人は悔い改めて使徒として立ち返り、もう一人は永遠の暗闇へ入ってしまったのです。この事実は、罪の恐ろしさ以上に、悔い改めようとしない心の頑なさこそが何よりも恐ろしいのだと教えています。
張ダビデ牧師は、この本分から「最後まで立ち返らない罪人を見つめる神様の痛み」を強調します。全知全能なる神様なら、人間を無理矢理悔い改めさせて引き戻すこともできるのではないか、と私たちは考えがちです。しかし愛で治められる神様は、そのような方法をとられません。神様は私たちに自由意志を与え、その自由の中で真の愛の関係を結ぶことを望んでおられます。ですから人が罪の道を選ぶならば、神様は胸が引き裂かれるような痛みを覚えながらも、その選択を止められないのです。これこそが「愛の世界」、すなわち「神の国」の本質でもあります。強制的に操作される世界ではなく、愛をもって招きながら、最終的な選択は各人に委ねられる世界だからこそ、悔い改めなければ永遠に暗闇にとどまってしまう悲劇的な結果も生じうるのです。
もう一つ注目すべき点は、晩餐という共同体的な交わりの現場がいかに重要であるかということです。晩餐は単なる食事の場ではなく、霊的に心を分かち合い、主の御言葉を共に黙想する場でもあります。イエス様と弟子たちは過越の食事を共にしながら、誰が偉いかを論じ合っていた弟子たちの足を洗い、仕える模範を示され、神の国のビジョンを改めて弟子たちの心に刻まれました。それだけでなく、裏切りの影があることを警告してもおられました。私たちの礼拝や聖餐、交わりの場も同様に、私たちが霊的に目を覚ましていられるよう助けるはずの機能を担うべきなのです。私たちが共に御言葉を分かち合い、互いのために祈り合い、互いの魂の状態を気遣う過程の中で、罪の種が芽生える前に気づいて悔い改めに導くことができます。それが愛の共同体の務めなのです。
しかし晩餐の温かさと安心感が、むしろ私たちを油断させる場合もあります。弟子たちは気楽な食事の席で、主が語っておられる言葉の本質を深く考えるよりも、その場の見える行為だけに注目していた可能性があります。「足を洗ってくださる主の謙遜さ、パンとぶどう酒を分け与える恵み、互いが交わす親密な会話」などに目を奪われ、ユダが闇へと落ちていく現実はまともに理解できていなかったのかもしれません。私たちも自分たちの礼拝や交わりの場において同じ状況に陥る可能性があります。御言葉を聞いてもすぐに忘れてしまい、交わりの中でも上辺の挨拶だけで済ませ、誰かが霊的危機や苦痛に直面していても、真剣に心を寄せないのです。そうなると愛の勧めが実質的に働かず、その人の魂は誰にも気づかれないまま闇へ沈んでしまうかもしれません。
張ダビデ牧師はここで、互いが互いの「霊的な鏡」となろうと訴えます。イエス様が弟子たちに「互いに愛し合いなさい」と言われたことは、抽象的なスローガンではありません。その愛の中には、相手の罪や弱さを見て見ぬふりをせず、悔い改める機会を与え、ときには厳しく諭しつつ、最後まで共に歩むという決意が含まれています。こうした努力が存在するとき、私たちの共同体はユダのような霊的悲劇が起こるのをある程度防ぐことができます。しかし誰も目を覚ましておらず、互いを顧みないのであれば、ユダは"ひとり"裏切りの道へ出て行ってしまい、その闇に誰も気づかないまま手遅れになるのです。
振り返れば、弟子たちはユダが去ってから後になって、ようやく多くのことを悟ったのでしょう。イエス様が「あなたのしようとしていることを、今すぐしなさい」と言われたのはなぜか、そのときは分からなかったかもしれませんが、後になってすべてがつながり理解できたはずです。けれどもそのときはすでに遅かった。ユダはイエス様を引き渡す計画を実行しに立ち去り、主は捕らえられて苦難の道を進まれることになります。罪が現実化するのはこうした流れで進みます。まず心の中に始まる罪の種は、最終的に行動へと移され、その行動は取り返しのつかない結果をもたらすのです。したがって、私たちは「罪が心の中に居座り始める初期段階」で気づいて悔い改めるよう、目を覚ましていなければなりません。
それでもなお、ヨハネの福音書13章に描かれたユダの裏切りの物語は、同時に私たちに深い希望のメッセージをも与えます。それはイエス様が示された愛の粘り強さです。イエス様は裏切りを知っておられながら、最後までユダから目を離されませんでした。最後の晩餐でも彼を最も近くに置き、パン切れに愛を込めて手渡されました。何とか彼を悔い改めさせたく、またその心を最後までつかもうと努力されました。もしユダがあの瞬間にでも心を変えるだけで、ペテロの失敗が回復されたように、ユダもまた回復された可能性があるのです。これこそ主の愛です。私たちもまた「立ち返る機会」を日々与えられているという事実が、誰一人として絶望に閉じ込められる必要がないことを示しています。
しかし同時に、その立ち返りの機会が永遠に有効だと勘違いしてはいけません。ユダは確かに最後の晩餐でパン切れを受け、そこに至るまでにも何度もイエス様の御言葉と愛のしるしに触れていました。それにもかかわらず、心を改めようとはせず、最後のチャンスさえも拒みました。これはまさに、霊的な暗闇が人間の内面にどれほど深く根を張り得るかを示す恐ろしい姿です。そして闇が現実化した瞬間、彼の魂は回復できない絶望のうちに飲み込まれてしまったのです。
このようにヨハネの福音書13章に描かれるユダの裏切り事件は、昔の弟子共同体内部で起こった衝撃的な悲劇というだけにとどまりません。むしろ私たち自身がイエス様の愛を日常的にどう受け取り、あるいはどう背を向けているのかを問いかけます。私たちは礼拝のたびに、御言葉のたびに、交わりのたびに、主の愛をパン切れのように受け取っています。御言葉を通し、共同体の礼拝を通し、宣教される福音を通し、互いに交わす愛の交わりを通して、主に立ち返る機会を絶えず得ているのです。ところがユダのように霊的無知や頑なさに絡め取られ、すべてのチャンスを逸してしまう可能性もあることを、常に覚えていなければなりません。張ダビデ牧師はこれを「神様の無力さ」とも呼びます。全能の神であっても、愛においては人間の自由意志の前で無力に見えざるを得ないことがあるというのです。しかしこの無力さこそが、神の愛のもっとも劇的な表れでもあります。無理に従わせるのではなく、人が自らの意思で戻ってくるのを待っておられるからです。
「ユダがそのパン切れを受け取ると、すぐに出て行った。すでに夜であった」(ヨハネ13:30)というヨハネの福音書13章30節の言葉は、私たちに決断を促す御言葉として迫ります。日々多くの決断をする人生の中で、私たちは主の勧めに従って立ち返るのでしょうか。それとも最後まで背を向けて闇を選ぶのでしょうか。それがユダの裏切りの物語が突きつける究極の問いです。張ダビデ牧師が強調するように、私たちの内にユダのような頑なさが潜んでいないか、日ごと御言葉と祈りをもって点検しなければなりません。そしてどんなときにも、主の愛が最後まで私たちに向けて開かれているという事実を絶対に忘れてはなりません。裏切りが闇へ向かう選択だとすれば、愛は光の道で私たちを引き留める招きなのです。どちらの道を選ぶかという決断は、私たち自身に委ねられています。
こうした教えは、すなわち私たちに「常に目を覚まして自分自身を省み、互いを気遣い、御言葉と祈りによって交わりを深めなさい」という結論を突きつけます。どんなに愛の共同体と言われる場であっても、裏切りが起こり得ることを忘れず、誰かの心が揺らぎかけたときにそれを支え、悔い改めに導くのが真の仕え合いであり、愛の実践です。そして個人としても、ユダのように御言葉を損得勘定で受け取ったり、愛の行いを世俗的観点で評価しようとしないよう、毎日主の御前にへりくだる必要があります。「ユダがそのパン切れを受け取ると、すぐに出て行った。すでに夜であった」という言葉が、私たち個人の最終的な結末とならないようにするためにも、私たちは主の愛をつかみ、最後まで悔い改めて立ち返る道を選び続けなければならないのです。まさにそれがヨハネの福音書13章に込められた切実な勧めであり、張ダビデ牧師が強調する核心的メッセージなのです。

















